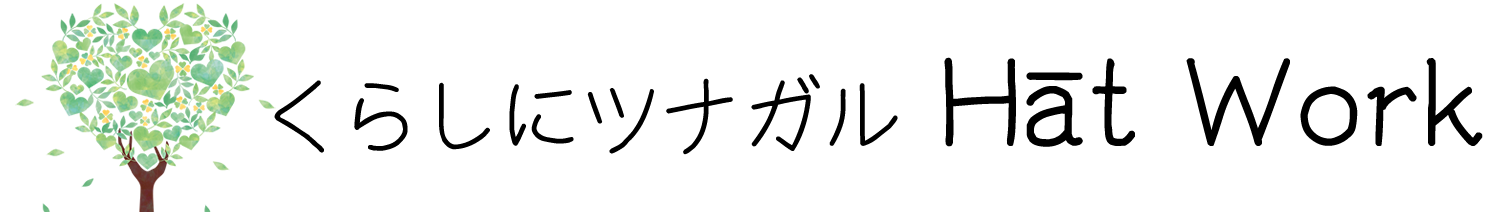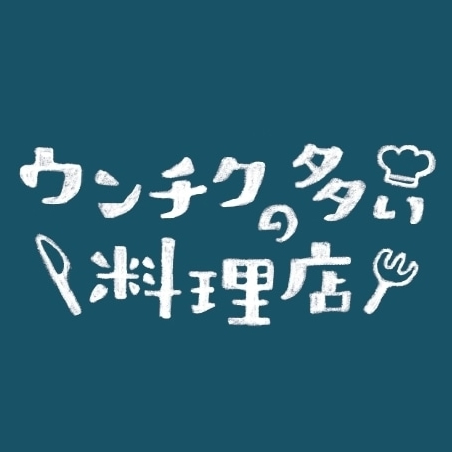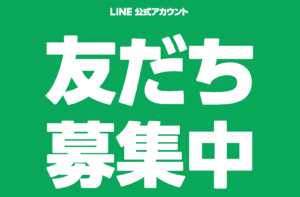アナキストの思想家として著名であるピョートル・クロポトキンが1902年に著した本書は、今から100年以上前の古い著作だが、コロナ禍で社会の制度に頼れなくなった際、扶け合いの重要性が唱えられたこともあって、再度脚光を浴びている。
本書はアナキストとしての著作というより、むしろ自然地理学や生物学を学び、長期間のフィールドワークを元に著している。
動物が群れを作って助け合う姿や、中世のギルド、農村共同体での共同作業を例にとり、相互扶助が社会発展の基盤であるとした。その視点は、過度な競争社会がもたらす格差や孤立感に対する批判として現代でも依然として有効だろう。
少々長くなるが、序論にこの書のエッセンスがあるので引用する(英訳されたものを自訳)。
ご近所に火事のある時、バケツに水を汲んで駆けつけるのは、見も知らない隣人に対する愛からではない。愛よりは漠然としているが、もっと広いもの、人間的な連帯や公共心の感情、もしくは本能が私たちを動かすのである。反芻動物や馬の群れが狼の攻撃に抵抗するために輪を作ろうとするのは、愛でもなければ固有の意味での同情でさえもない。狼が狩りのために群れを作ろうとするのも愛ではない。子猫や子羊が遊ぶのも、数種の若い鳥が秋に一緒に日々を過ごすのも愛ではない。フランスほどの広大な地域に散らばっている何千頭ものダマジカが、川を渡るために特定の場所に向かって行進する数十の別々の群れを作ろうとするのも、愛でも個人的な同情でもない。それは愛や個人的な同情よりもはるかに広い感情であり、非常に長い進化の過程で動物と人間の間でゆっくりと発達した本能であり、動物と人間の両方に、相互扶助と支援の実践から得られる力と、社会生活で見いだせる喜びを教えてきた。(中略)人類社会の基盤となっているのは愛でも同情でもない。それは、たとえそれが本能の段階であっても、人間の連帯の良心である。それは、相互扶助の実践から各人が借りている力、各人の幸福が全員の幸福に密接に依存していること、そして、個人が他のすべての個人の権利を自分の権利と同等と考えるようになる正義感や公平感を無意識に認識することである。この広く必要な基盤の上に、さらに高度な道徳的感情が発達する。
こうした形の相互扶助は、国家の制度に依る解決策や経済社会の対価を伴うサービス提供に過度に頼らず、個々人が自発的に参加し、互いのニーズを補完する仕組みとして再定義される必要がある。それは、単なるチャリティや一時的な支援を超え、人間の本能として、持続可能な協力関係を築くことを意味する。
大正時代の翻訳版を最初に読んだので、読み解くのが難しかったが、社会不安にあふれる現代に、市民活動に携わる人にはぜひ読んでもらいたい一冊だと思う。新訳版には、「ブルシット・ジョブ」や「万物の黎明」を著したD・グレーバーの序文も付いているのでもう一度じっくり読んでみたい。
●出版社のサイト
■大杉栄 訳版(同時代社 刊)
1924年の翻訳なので文体が古いが格調は高い。
■小田 透 訳版(論創社 刊)
2024年の新訳。現代語訳の上に人類学者のD・グレーバーとA・グルバチッチの序文が収録されていることもあっておすすめ。
●参考図書
「相互扶助再論 支え合う生命・助け合う社会」(クロポトキン著 大窪一志訳 同時代社刊)
クロポトキンの関連論文を集めた論考集