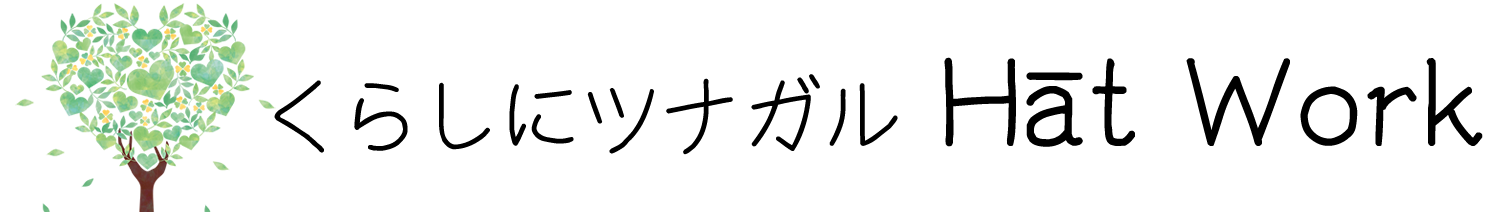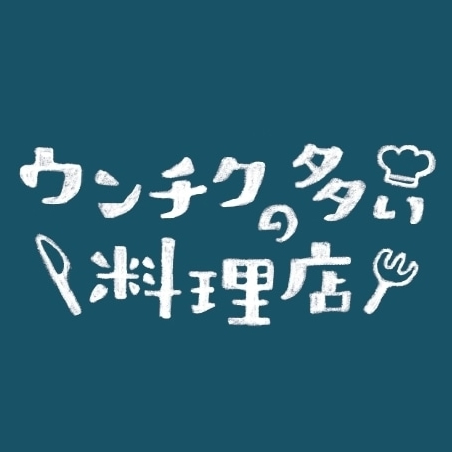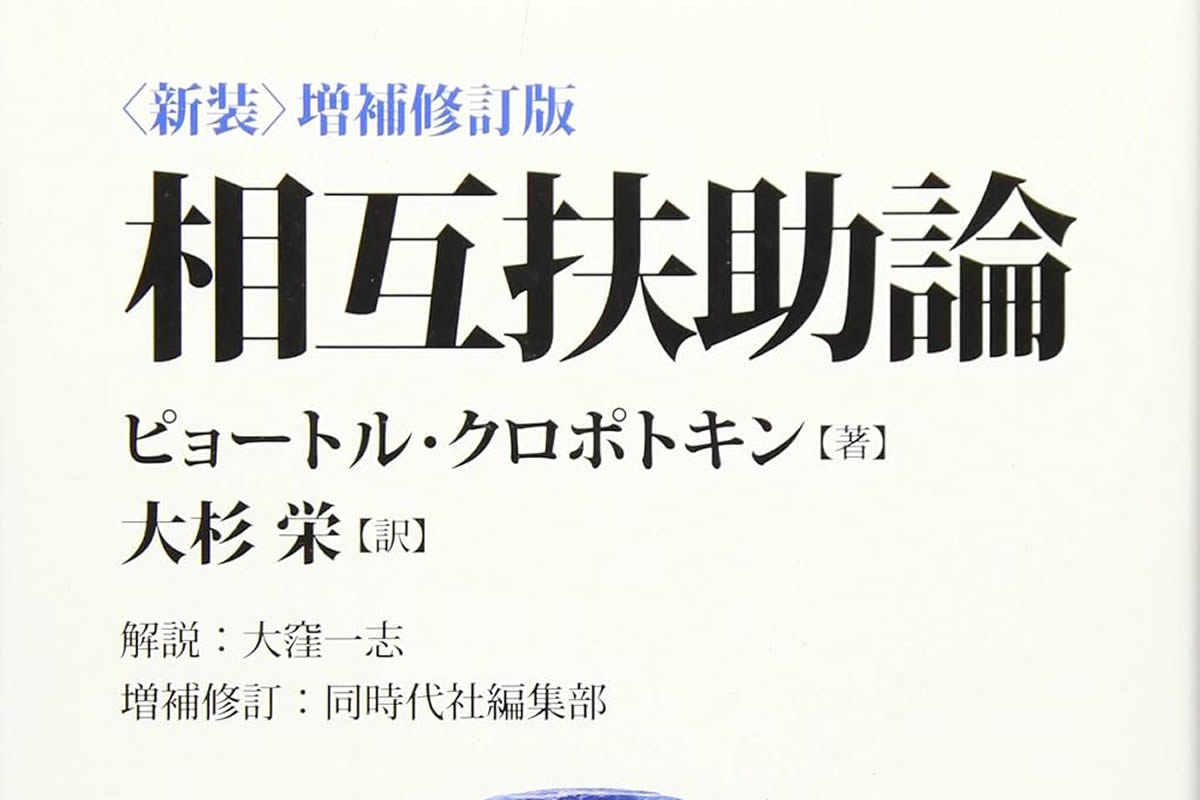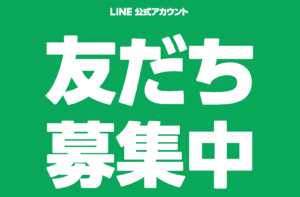シャプラニール=市民による海外協力の会のオピニオン誌「もうひとつの南の風 Vol.27」に寄稿した文章(2025年3月)をこちらにも掲載。会員向けの会報誌「南の風」では伝えきれなかった海外活動の情報や動きのほか、役員・会員の活動を報告しているもので、現在はオンラインで公開している。
市民社会と相互扶助
はじめに現代社会の課題と相互扶助の必要性
現代社会は、気候危機による多発する災害、「不安な社会」の現れとしての内向性やポピュリズムの言説への迎合、高齢化や孤独の増大、経済格差など、多様化・複雑化・深刻化する課題に直面している。加えて国際的な政治的・経済的構造の変化と対立の激化により、先行きが見えない状況にもある。
これらの問題は、国家や経済社会だけでは解決が難しく、制度に依るアプローチでは対応しきれない限界が露呈している。一方で、市民一人ひとりが主体的に関与し、互いに支え合う「相互扶助」の仕組みがふたたび注目されている。
ピョートル・クロポトキンは、『相互扶助論』(1902年)で自然界や人類史において競争よりも協力が生存と発展の鍵であったと説いた。古い著作であるものの、コロナ禍で社会の制度に頼れなくなった際、扶け合いの重要性が唱えられたこともあって、再度脚光を浴びている。
また、現代ではブロックチェーン技術を活用した自律分散型組織(DAO)が、階層的な統治を排し、透明性と参加度を高めた新たな相互扶助の形として注目を集めている。
本稿では、こうした視点を取り入れつつ、事例を踏まえ、市民社会がどのように相互扶助を構築していくべきかを考える。
相互扶助の理論的基盤:クロポトキンの視点
クロポトキンは、アナキストの思想家として著名であるが、「相互扶助論」は、むしろ自然地理学や生物学を学び、長期間のフィールドワークを元に著した。少々長くなるが、序論にこの書のエッセンスがあるので引用する。
ご近所に火事のある時、バケツに水を汲んで駆けつけるのは、見も知らない隣人に対する愛からではない。愛よりは漠然としているが、もっと広いもの、人間的な連帯や公共心の感情、もしくは本能が私たちを動かすのである。反芻動物や馬の群れが狼の攻撃に抵抗するために輪を作ろうとするのは、愛でもなければ固有の意味での同情でさえもない。狼が狩りのために群れを作ろうとするのも愛ではない。子猫や子羊が遊ぶのも、数種の若い鳥が秋に一緒に日々を過ごすのも愛ではない。フランスほどの広大な地域に散らばっている何千頭ものダマジカが、川を渡るために特定の場所に向かって行進する数十の別々の群れを作ろうとするのも、愛でも個人的な同情でもない。それは愛や個人的な同情よりもはるかに広い感情であり、非常に長い進化の過程で動物と人間の間でゆっくりと発達した本能であり、動物と人間の両方に、相互扶助と支援の実践から得られる力と、社会生活で見いだせる喜びを教えてきた。(中略)人類社会の基盤となっているのは愛でも同情でもない。それは、たとえそれが本能の段階であっても、人間の連帯の良心である。それは、相互扶助の実践から各人が借りている力、各人の幸福が全員の幸福に密接に依存していること、そして、個人が他のすべての個人の権利を自分の権利と同等と考えるようになる正義感や公平感を無意識に認識することである。この広く必要な基盤の上に、さらに高度な道徳的感情が発達する。(*1)
こうした論から、ダーウィンが取り上げた「適者生存」の論が競争のみを意味するのではなく、種の存続に相互の協力が不可欠だと主張した。
序論に続く本論でクロポトキンは、動物が群れを作って助け合う姿や、中世のギルド、農村共同体での共同作業を例にとり、相互扶助が社会発展の基盤であるとした。
クロポトキンの視点は、過度な競争社会がもたらす格差や孤立感に対する批判として現代でも依然として有効である。例えば、経済的成功を個人単位で追求する新自由主義的な価値観は、貧困層の切り捨てや社会的不信を増幅させている。一方で、後述する子ども食堂など地域の助け合いや災害時のボランティア活動などは、市民社会における相互扶助が現代でも根強い力を発揮することを示している。
こうした形の相互扶助は、国家の制度に依る解決策や経済社会の対価を伴うサービス提供に過度に頼らず、個々人が自発的に参加し、互いのニーズを補完する仕組みとして再定義される必要がある。それは、単なるチャリティや一時的な支援を超え、人間の本能として、持続可能な協力関係を築くことを意味する。
DAOによる実践的可能性:技術と自律の融合

デジタルテクノロジーの世界では、非中央集権化(分散化)を基本思想とするweb3が新たな潮流として登場している。その中でも相互扶助を実現する現代的なツールとして、自律分散型組織(DAO)が注目されている。DAOは、ブロックチェーンという技術を基盤に、中央の管理者を置かずに参加者がルールを共有し、透明な意思決定を行う組織形態である。
DAOが相互扶助に寄与する可能性は、主に次の3点にある。第一に、透明性と公平性である。従来の組織では、意思決定が特定の人物やグループなりに偏ったりしがちだが、DAOではすべての取引や決定が公開される。これについては、NPO法人も民主的な意思決定と公開の仕組みを制度的に持っているが、自動化されている点に特異性がある。第二に、参加への敷居が低いため、参加度を高めやすい。地理的制約や階層を超えて、世界中の市民が対等に参画できる(ただしDAOの仕組み自体を把握する必要はある)。第三が柔軟性である。小規模なコミュニティから始まり、必要に応じて規模を拡大することもできる。
例えば、児童労働反対をテーマとして考えるとすると、DAOによる世界的な市民運営が可能だろう。世界中の市民が資金を出し合い、世界的なキャンペーンのプロジェクトを提案・投票で決定し、進捗を追跡する仕組みが考えられる。このような取り組みは、クロポトキンの言う「自発的協力」を技術的に具現化したものと言える。
DAOによる相互扶助は、課題を抱える当事者間による場合もあれば、それを支援する側による場合もある。実際、NGOの中でも法人自体の組織運営としてではないが、資金調達の一環としてDAOを取り入れた事例が出てきている(NPO法人エイズ孤児支援NGO・PLASの「PLASDAO」)(*2)。
もちろん、DAOが一般市民に拡がるにはまだ課題もある。技術的に理解が難しいことや、意思決定の際に積極的に参加する人ばかりでない場合は公平性を損なう恐れも出てくる。克服のためには、使いやすい仕組みづくりや学習に加えて技術を使わないアナログな取り組みとのバランスが求められるだろう。
日本における相互扶助の事例
子ども食堂:地域住民による共助の場
子ども食堂は、子どもが一人でも行ける無料または低額の食堂で単なる栄養補給のみではなくコミュニケーションの場、居場所となっている取り組みで、2012年に東京都大田区の「気まぐれ八百屋だんだん」で始まり、地域住民やNPOが主体となって全国に広がった。2024年12月現在の10,867カ所で開設されている(NPO法人全国こども食堂支援センターむすびえによる調べ)。この数は公立の中学校・義務教育学校の数を上回っている。
多くの子ども食堂が、ボランティアが食材調達から調理までを担い、子どもだけでなく高齢者や親子も参加する多世代交流の場となっている。これは、クロポトキンが描いた「自由な連合」に近い形であり、競争社会の中で孤立した個々をつなぐ役割を果たしている。地域住民の自発性がその基盤を支えている点で、相互扶助の現代的実践例と言える。
「静岡方式」:ニート・引きこもり支援の市民ネットワーク
NPO法人青少年就労支援ネットワーク静岡が展開する「静岡方式」は、働きたくても働けない若者(ニートや引きこもり)を地域のボランティアが伴走型で就労を支援する取り組みで、現在は2,000名以上のボランティアが登録し、年間1,000人以上の若者を支援している。その特徴は、①若者本人の希望を優先して個別支援を行う、②地域の市民ボランティアによる伴走、③就労後の定着支援である。
例えば、セミナーや就労体験を通じてボランティアが若者との信頼関係を築き、求人をしている企業との橋渡しを行う。支援を受けた若者の7~8割が無業から脱し、働く喜びを実感している。
「静岡方式」について、初代理事長の津富宏は次のように記している。「青少年就労支援ネットワーク静岡にとって,就労支援は目的ではなく,相互扶助の社会をつくるための手段である。『働きたいけれども働けない』という課題は,今の社会において重要な課題であるのでそれに取り組むが,相互扶助の社会ができれば,たとえば,孤独死といった問題も解決することができる。つまり,どんな課題が社会にあろうと,それを解決できる相互扶助の社会をつくることが,私たちの目的である。(中略)静岡方式とは,相互扶助の市民社会というコモンズを,私たちの地域が有していた,共同体のイメージを喚起しつつ,再創造する取り組みである。これは,支援/被支援者モデルや提供者/顧客モデルによって,真ん中の隙間を埋めるのではなく,むしろ,新たに「共」的空間として,私たちの地域社会を再構築する試みであり,市場化の持つ排除の力を乗り越え,市民主体の地域をつくる試みである」(*3)
この「地域は資源のオアシス」とでもいうべき理念は、クロポトキンの相互扶助論に通じる。中央集権的な福祉に頼らず、市民が主体的に関与することで、社会的孤立を解消し、自立を促している。
これらの事例から、相互扶助が地域のニーズに即した柔軟性と、市民の主体性を引き出す力を持つことがわかる。さらにDAOの考え方を取り入れれば、透明性や拡張する可能性もあって、国内においても全国的なネットワーク構築も可能だろう。
シャプラニールによる相互扶助
次にシャプラニールによる相互扶助の取り組みについて紹介する。1972年、シャプラニールの前身となるヘルプ・バングラデシュ・コミティが設立された後、現地での支援活動は試行錯誤を繰り返したが、79年になってさまざまな現地NGOが当時取り組んでいたショミティ(農村部の貧困層を対象とした相互扶助の小グループ)育成の方式を取り入れた。
ショミティは、経済的にも社会的にも弱い立場にある人が、お互いに助け合うことを目的として自分たちで作るグループであり、NGOはショミティを側面的に支援する形を取っていた。
シャプラニールもこのショミティを支援の受け皿として、年を経ながら定期的なミーティング、グループ貯金、保健衛生プログラム、教育プログラム、収入向上プログラムなどを提供していった。また、ショミティによる相互扶助の在り方が地域社会に波及効果をもたらし、自分たちの地域は自分たちでよくしていこうという機運が高まることも期待していた。
最終的には支援の手が入らなくても活動を継続できる(自立)ことをめざして、最盛期には800近いショミティを支援をしてきたが、自立できず解散するショミティも少なからずあり、シャプラニール自体の方針や社会情勢も変化する中で2003~2004年頃にはショミティ活動は漸減していった。理由はさまざまあるものの、相互扶助の営みに外部者(この場合はシャプラニール)がどうかかわっていくのかは大きな懸案として残った。本稿はこの懸案を解くことを目的としていないが、これまでに述べたような相互扶助の在り方を踏まえつつ、いずれ議論してみたい。
市民社会における相互扶助の構築
以上の理論と実例を踏まえ、市民社会で相互扶助を醸成する方法をいくつか提案したい。
1.地域コミュニティの再活性化
相互扶助の第一歩は、身近な地域でのつながりを強化することだ。国内で言えば、空き家を活用したコミュニティスペースやスキルシェアリングの場を設けて住民同士の信頼感を醸成する。特定の目的(子育て支援、コミュニティ防災など)を軸に自然発生的な協力関係をどう築くかが懸案となる。
2.ハイブリッド型DAOの導入
地域での活動をスケールアップするため、DAOを導入する。ただし、まだ新しい技術であることから、技術に不慣れな層を排除しないよう、アナログとデジタルのハイブリッド型とすることが望ましい。例えば、地域通貨をDAOで管理することで、まちづくりにおける経済の活性化と透明な資金循環を実現する。オフラインでの対話も併用することで全員が主体的に関与できる環境を整える。
3.学びの場づくり
相互扶助を重視する価値観を広めるには、前述のような事例を市民講座で紹介し、参加意欲を高める必要がある。
4.課題別のネットワーク形成
多様な社会課題に対応するため、テーマごとの相互扶助ネットワークを構築する。例えば、ヤングケアラーの状況改善をめざすグループやフードロス削減に取り組むグループなどが、それぞれDAOや地域単位で活動しつつ、必要に応じて連携する。この分散型ネットワークは、クロポトキンの言う「自由な連合」の現代版とも言えるだろう。
5.政策との連携
市民社会における相互扶助の取り組みを持続・発展させるには、政府や企業との協働も不可欠だろう。例えば、DAOで集めた資金に助成する制度や、相互扶助活動への税制優遇を求めるロビイングを行う。国家に頼りすぎず、市民の主体性を保ちつつ、現実的な支援を引き出すバランスが鍵となる。企業であれば、社員のプロボノ派遣や本社・支社のある地域への貢献なども考えられる。
おわりに 相互扶助を通じた持続可能な未来
現代社会の複雑な課題に対し、クロポトキンの「相互扶助論」は、競争社会への警鐘と協働の重要性を示す羅針盤となりえる。またDAOは、まだまだ一般に理解されるには時間がかかるであろうが、その理念を現代に実装する技術的基盤を提供する。地域での信頼関係を基盤に、技術を活用した拡張可能仕組みを構築することで、市民社会は新たな相互扶助の形を創出できるのではないか。
鍵となるのは、市民一人ひとりが受け身ではなく社会に主体的に関与する意識と、技術と人間性を調和させる柔軟性だろう。相互扶助の精神と実践が広がれば、持続可能な未来への第一歩となる。クロポトキンが夢見た相互扶助社会~自由で協力的な社会を、現代の市民の手で、具体的な形として再構築していきたい。
最後にオランダの歴史学者、ルトガー・ブレグマンの言葉を以て本稿を終えたい。
「信念を持って『世の中は変えられる』『こんな世界のままでいいわけがない』と考えることが、前よりもかっこいいものになってきている」 これからの世界にはまさに力を持たない一般市民が相互扶助をすることにより、社会変革の一助を担うことが必要となるだろう。筆者も他人事ではなく、自分のこととして社会に向き合っていきたい。
【註】
1.『相互扶助論』、ピョートル・クロポトキン著(1902)、同時代社(2017)もしくは論創社(2024)、当該部分の翻訳は英訳から著者
2.PLASDAO https://financie.jp/users/plas (2025年3月22日閲覧)
3.『静岡方式による就労支援―「半福祉・半就労」から、「脱福祉・脱就労」へ―』、津富宏(2019)、社会政策学会誌『社会政策』第11巻第1号所収
■オピニオン誌「もうひとつの南の風」
■クロポトキン「相互扶助論」